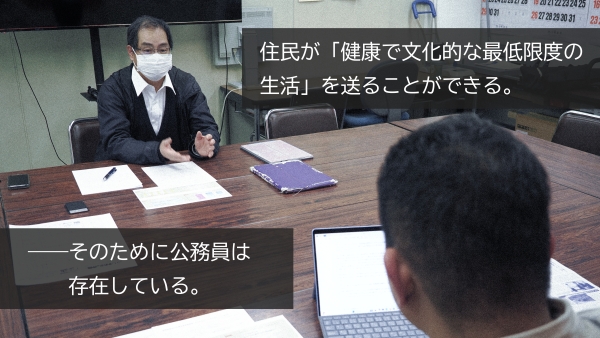
自治労連
最後に、最低賃金というのは、都道府県ごとに設定されていますけど、我々は全国一律にして、格差のない最低賃金にすべきだという運動をしています。でも、これもきちんと言い始めたのは、たぶん2010年で、結構、最近になってからだと思います。どちらかというと、いま全労連は「最賃上げろ」よりも「全国一律最低賃金の実現」を主に言っていると思うんですが、自治労連としては、やはり地域格差をなくすということのねらいの一つに、地域手当を改善して、それを将来的にはなくしていく。当然、地域手当部分を基本賃金に組み込んで、公務員賃金とはこういうものだ、というところを全国的に一律化していくということをめざしているのですが、それに対して中澤先生の考え方をお聞きできればと思います。
 中澤
中澤
まず前提として、県ごとの格差は歴然とあるわけです。そもそも賃金構造基本統計調査とかで労働者の平均賃金を見たときに、東京とか大都市部は賃金水準が高いんですよ。逆に、地方の人口の少ないところは、賃金水準が低くなっている。
では、この格差を縮めるべきなのか、そのまま放置しておくべきなのかっていう…。自分がどちらの立場に立つかって言ったら、やはり格差は縮めるのが是だと思うんですよ。実際、いままでの我々の社会も格差はなくしていこうと、そういうふうに向かってきたわけです。社会がより良くなっていくためには、格差をもっと広げていこうなんていうことは普通、ありえない。格差はなくしていくっていう方向性だと思うんですよ。
例えば都市部と地方との格差は、やはりできるだけなくした方がいいと考えるならば、制度はやはり全部揃えていかないといけないわけです。そういうふうに人為的に変えて、格差を是正する方向に進まなければいけないので、最低賃金がかなり大きな影響をもたらしたわけです。元凶と言っていいのかわからないですけど、47都道府県に格差がついているのは、それぐらい大きな影響力を持っている。
格差を縮めなければいけないという理念が正しいということならば、最低賃金は揃えて、できるだけ格差がなくなっていく方向に持っていかなきゃいけないんです。
中澤
そして、最低賃金だけではなく、地域手当も然りですし、生活保護もそうです。地域ごとに差をつけるということの悪影響がすごく見えてきているので、できるだけ改善・是正していく。もしくは、もうなくしていくべきです。一つのものには一つの物差しで考えるということにシフトしていかなければいけない。
最低賃金に関しては、最低生計費調査によって生計費にほとんど差がないというエビデンスを提供して、最賃1500円以上にという運動の後押しになった。特に地方にとって、格差を縮めて地方経済を再生させるということをめざすならば、全国一律制度にしていくというのはマスト(欠かせないもの)ではないでしょうか。
自治労連
いまの経済というか、お金に関わる国のいろいろな制度というか考え方というかが、新自由主義のもとでの個人主義的な考え方というのをベースに制度がどんどん新たに組み立てられてきたというのは、この間、ずっと思っていました。
本来の社会保障の存在から外れて、「社会保障」という言葉の中で、違うものになってきてしまった。
中澤
いや、もうほんとそうですよね。
自治労連
よく労働組合が使う言葉だと、社会保障って第二の賃金。もっと専門的に言えば富の再分配とかだと思うんですけど、いま、そういう機能じゃなくて、応益負担…。いや「応益」じゃないよ、と思うんですけど、社会保障すべてが、利益を受ける人が負担するべきだ、みたいな方向に作り替えられてきてしまったというか。いま、それを反省するべきですよね。
中澤
それが本当におかしいんだということを言わなければいけなかったんです。けれど、もう90年代の後半くらいから…、いや、もう80年代からそういうのが進んでるんですけど、社会保障とは何ぞやという根本のところが、やはり自助・共助・公助。自助と共助を全面に出してきて、その価値観がもうかなり浸透してるんですよ。
そもそも社会保障って何だと言えば、自助だけでは生きられないから、公助としての社会保障が歴史的に登場するわけなんですよ。そもそもの社会保障が出てきたことを考えれば、なぜ自助が最初に来るの、という。もうそこがもうおかしいわけです。
自治労連
人間が自助で生きるのは、本来、当たり前なんですよね。それができないから、みんなで助け合おうっていう共助というものが出てきた。そして、そのためのシステムということで社会保障ってできたわけじゃないですか。そもそも、助け合いじゃなくて、自分で何とかしろよというのが前提になってるのが…。
 中澤
中澤
まず、そこがおかしいんですよ。そういうのは、資本主義が進化するなかで、自助だけでは生活できなくなった。いろいろな問題が出てきて、格差が大きくなりすぎて、戦争が起こって…。そういう反省のもとに、人間らしく生きる権利の核となる社会保障という政策が出てきたわけです。そういう意味では、全国一律にするということもそうですし、普通に暮らすことができる水準にしていくという、そこが大事な価値観だと思います。勝ち組が全部取っていけばいい、ではなく、やはり再分配していかなければいけないんだというところを、どうやって分かってもらえるのかなっていうのは思います。
格差があることによって、結局、東京なり、地方で言えばその中核都市が独り勝ちをする。格差があることによって、高いところにどんどん集まりますから。それをよしとするのか、東京一極集中がいいのか。静岡県だったら、静岡市とか浜松市だけに人が集まって、そこだけ賑わえばいいのか。やはり取り残されるところが出てくるわけなので、そのことをもっと地方の人たちも考えていかないといけない。
中澤
地方経済を再生しなくていいって考えているならいいですけど、静岡に住んでいる多くの人って、静岡のこと好きじゃないですか。静岡がもっと賑わえばいいと考えている人はたくさんいるわけです。それを本当に願うんだったら、いまの社会制度はやはりおかしいので、賃金や社会保障のバラバラの制度を、統一したものに変えていくことをめざさなければいけない。その地域の再生と絡めて、そんな話をもっと言わなければいけないのではないかなと思います。
自治労連
株式会社「資本主義」で誰が儲けるかって話になると、自分たちが儲からないので、そちらに誘導しようっていうのは当然あると思うんですよ。
中澤
この間ずっと(公共が)破壊されてきたので、そこに対抗していかないと。
自治労連
本来その役割って自治体が担わなきゃいけないと思うんですよ。
中澤
公務員バッシングをしてきて、公務員の賃金は自分たちの税金から払われているから、なるべく少ないほうがいいとか、そこがもっと削れるというのをやってきた結果、結局、自分たちがまたツケを払わされて、サービスが低下して、というところに、公務じゃない人たちももっと気づかなきゃいけない。
自治労連
そうなんですよ。よく自治労連も言うんですけど、自分たちが受ける公共サービスが低下してきたというのは、いま中澤先生がおっしゃった通りなんです。もう一つ重要な視点というのは、公務員というのは基本的にそこに住んでいる人たちなので、イコール住民であって、かつ、(地元企業にとっての)お客さんであるはずなんですよね。
中澤
そうなんです。その人たちのことを忘れているというか、視野が狭くなっているんですよ。自分たちの税金を使っているみたいに感じているんですけど、自分たちの商品を買っている人でもある。地域の経済を支えてくれているわけで、やはり自治体・公務公共関係労働者がすごく経済を活性化させている重要な存在なので、そこが潤えば自分たちも潤って、地域が全部良くなるわけです。その逆のことをしてきた結果が、自分たちの首を締めてきたわけじゃないですか。
自治労連
東京とか大都市部のところで公務員がいなくても生きていけるんです。そうですよね。でも、そんな地方が全国に一体どれだけあるのかという話じゃないですか。やはり健康で文化的な最低限度の生活ができるようにするということのために公務員って存在してるんだというところは、自治労連としてはすごく言いたいんですよ。でも、自分たちが助けたいと思っている人たちは、生活が苦しい人たちでもあるので、公務員を叩いているんです。
中澤
ほんとそうですよね。
 自治労連
自治労連
でも最低賃金が生活にどう関わってるかとか、地域間格差っていうのが、逆に地域をどんどん衰退させてるという、いろいろな話をさせてもらって、2025年の春闘で最低賃金の問題をやりたいと。なぜかと言ったら、いまさらですけど、公務労働者って春闘で賃金が上がらないんですよ。なので、公務労働者が春闘をたたかう意味というのが、ちょっとわからなくなってきているので、それを出したかったんですよ。
中澤
なるほど。大事なことですよね。
自治労連
今日は本当にありがとうございました。





 前のページ
前のページ

















