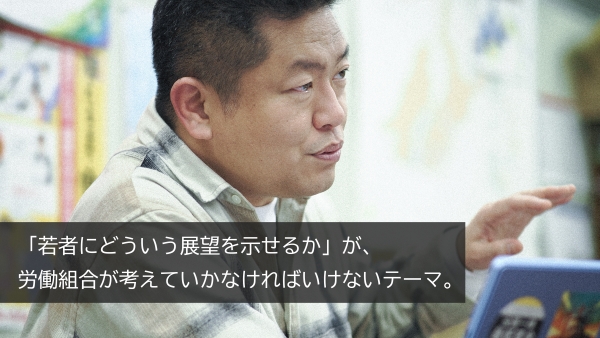
自治労連
次ですが、賃金や最低賃金と社会保障の関係はどういう関係にあるかというのは、中澤先生だったらどうやってお話ししていますか。
 中澤
中澤
まず大きい話で言うと、我々の生活というのは賃金だけで成り立たせるものではないです。日本はもともと賃金に依存した社会だったので、企業に正社員として勤めて、賃金をもらって、その賃金で自分とか家族の生活を賄うということがよしとされてきたし、企業の福祉がすごく手厚かった。でも、企業がだんだんそこのところを切り始めてきた中で、やはり賃金と社会保障の両方で生活が成り立つということが大事です。賃金も大事だけど、社会保障も大事っていうのは、それはもう欧州では当たり前なんですよ。賃金と社会保障で生活が成り立つっていうのが当たり前なんですけど、日本の場合は賃金だけで成り立たせようとしてきたので、社会保障がすごく疎かにされて、現在の日本の社会保障の脆弱さになるわけで、もっと充実させていかなければいけない。まず、これがあると思います。
ミクロというか、もう少し小さい視点で言うと、賃金と社会保障、最低賃金と社会保障というのが すごくリンクしているというか、密接な関係になっている。最低賃金が上がれば、年金とか生活保護とかの社会保障制度が充実していくけれど、その反対もあるわけです。最低賃金が低くなっていけば、社会保障の水準も下がっていく。だから最低賃金と社会保障は、やはりお互いに高め合うことが大事です。このことは、もっと言わなければいけないと思います。
自治労連
その一方で、いわゆる自己責任論的なのが当たり前の中で、小中学校、高校、大学を出て、社会人になっている世代が、いまかなり増えているわけじゃないですか。要するに「自分たちの税金で、例えば生活保護の人たちを養ってるのが納得いかない」みたいな人とかが、特に若年層に増えているっていうのはどう考えますか。
中澤
いまの若年層って、昔に比べると負担率がすごく増えてるんですよ。がんばって稼いだのに、こんなに取られている。自分たちも我慢させられているわけですよ。それなのに、自分たちから持っていったお金が生活保護などに使われているというのが納得いかないと。
この間ずっと「新自由主義」がいき過ぎぐらいまで広がって、浸透していく中で、そういう新自由主義の考え方や価値観が当たり前の世代が増えてきているわけですよ。「最低賃金を上げろ」なんて要求するより、「賃金が高いところに転職して、自分で高い賃金を手に入れればいい」と、そういう考え方が、まさに新自由主義的な考え方なんですけど、やはりそこが浸透してしまっている。これを変えるのは結構大変だなぁ、と。
自治労連
賃上げや社会保障の充実よりも、同じだけの時間使って働くんだったら、もっと効率のいいところで働けばいい、ということですよね。そういう人が公務員にも増えているんです。彼らの中では、なぜ労働組合の活動に協力しないのかといえば、時間がないんですよ。働いてる人たちはみんな同じですけどって言っても、彼らは、例えば仕事終わった後にも「リスキリング」とかで、自分の資格だったり技能だったりとかを高めているんですよ。それだと「労働組合の活動なんかしている時間がない」という人が、以前に比べてものすごく増えてて。「ちょっと待って、公務員ですよね」と思うんですけど。
一つは、同じ公務の中でもより高い賃金がある自治体に移る。例えば今回浜松市に就職したんだけど、浜松市は地域手当が3%、静岡市は6%なんですよ。で、浜松から静岡に移ったら、同じ仕事していても3%賃金が高いという話なんですよ。単純な話ではないので実際は違うんですけど。
そして、これが名古屋に行ったら15%になり、東京の23区に行ったら20%になるわけですよ。というところで、同じ仕事するにしても、あっちの方が得、という考え方になる。実は公務から違う仕事に行く人も多いんだけど、一度公務職場に入ったにもかかわらず、その自治体から別の自治体に行っちゃう人が決して少なくない、というのが実態としてあります。
それは、それこそ生計費や最低賃金の問題と同じで、賃金の高い首都圏に近いところに行くと、あっちの方が生活にかかる費用は東京の方が高い。例えば住居費とか、すごく高いですから。それは分かってるんだけど、それを補って余りあるぐらい賃金の水準が向こうの方が高いんだという人たちがいる。
 自治労連
自治労連
例えば、いま自治体でいちばん人材確保に困難が生じているのは,土木技術者なんですよ。これは本当に、県内どこの自治体に聞きにいっても、どんなに募集条件を良くしても来ないって言うんですよ。
東京なり首都圏なりの大手建設会社とかの賃金水準が、もう公務員とか比較にならないレベルで高い。
だから自治体で、10%上げました、15%上げましたっていうレベルでは全然追いつかなくて、まったく応募がない。自治体は、資格職、特に土木技術者とかが必要なのにもかかわらず、採用できない。どこの自治体でも、少なくとも1人、2人は欲しいんですけれど、来てくれない。そんな安い給料で働く理由がない、ということです。ものすごく問題ですよ。
昔は公務員といえば安定して、働き続けられるというところがあったと思うんですけれど、いまだと、同じところに長く働き続けようという感覚を持つ若年層がすごく少ない。
そこに将来60歳…、いまは65歳ですけれど、そこまで働き続けようなんていうことを最初から考えて就職してきている新規採用職員が、ほとんどいないです。
公務員でさえ、この状態ですから、民間企業はもう…。価値観の違いが大きいというのは感じます。
中澤
普段、大学生、若い人たちに接してますけど、やっぱり価値観が変わったな、というのは感じます。「コスパ」とか「タイパ」といった言葉がありますけど、本当にそこに気を使っている。空き時間というのをすごく嫌うし、お金にもシビアだし。やはり、自分のことにお金を使いたいとか、自分のために時間を使いたいという価値観は大きくなっているという実感があります。
それは、個人主義というか、自分がよければいいというところが出てきやすくて、やはり新自由主義とすごく親和性があります。
だから、他の誰かと連帯して繋がって、社会を変えていくという発想がなかなか出てきにくいんだろうというのを感じるんです、その時に、どういう道というか、展望を示せるのか。どうすれば若者を引き付けられるのかというのは、これから労働運動が考えていかなければいけないテーマですよね。
自治労連
いま中澤先生も言ったけど、みんなでがんばって、努力というかみんなで協力して物事を変えさせるっていうよりは、自分がこっち側に行って変わった方が早いみたいな感じですね。
中澤
だから、社会を変えるとかいう発想が出てきにくいことは事実だと思うんですけど、でも一方で、やはりそういうことに関心を持っている若年層もいるので、全く希望を持てないわけではないと思います。
自治労連
特に気候の問題とかは、若い人も、何とかしなきゃならない、そのためにはみんなで何とかしていこうというのが打って響いているような気はするんですよね。
これは、自分が変わってもどうにもならないことが分かっているということでもあると思いますけど。自分がこっちの自治体に変わったことで、温暖化がよくなるわけでもないですからね。
次のページ >>
公務労働者が春闘をたたかう意味がわかってきた





 前のページ
前のページ

















